親の学校子育てコラム

どんな子に育ってほしいですか?
子どもが小さな頃は思いやりのある元気な子に育ってほしい。
ただそう願っていたけれど…。
いざ子どもが小学生、中学生になると、思いやりや元気だけじゃなくて、自分のことは自分でする、自分で考えて行動する子になってほしいと感じる親御さんは多いのではないでしょうか。
目指すは、自分のことは自分でする、自分で考えて行動出来る子
でも現実は……
言われないとやらない自分で考えない子どもにイライラ……
「どうしたら自分で考えて行動するようになるんだろう…」
と頭を抱えている親御さんも多いのではないでしょうか。
▶ここでは、お子さんが自分で考えて行動するヒントをお送りします。
テーマは「自分で考えて行動する子」
キーワードは「自主性」と「主体性」
ぜひ、家庭の教育方針を考える上でも参考してもらえたら嬉しいです。
▼ではまず最初に、よく聞く親御さんのお悩みをご紹介します。
やり始めても…
「お母さんこれでいい?」
「これはどうするの?」
と何度も同じことを聞いてくるんです。
自分で考えられないんでしょうね。
私もイライラしてきて
「何度も言ってるでしょ!!自分で考えてやりなさい!!」
って言うんですけどね…
自分で考えてほしいし、家庭の教育方針としてあまり手を出さないようにしているのでしばらく放っておくんです…
でも結局やらないから言うんです。
「困るのは自分でしょ!どうせやるなら言われる前にやりなさいよ!」
最後は半泣きで愚図りながら準備をするんです。
自分で考えて行動する子になってほしいけど…
せめて、人に言われなくても、自分のことは自分でするようにしてほしいんです。
さあ、こんな時あなたならどうしますか?
自分で考えて行動できる子になるために!
知っておきたい「自主性」と「主体性」の違い
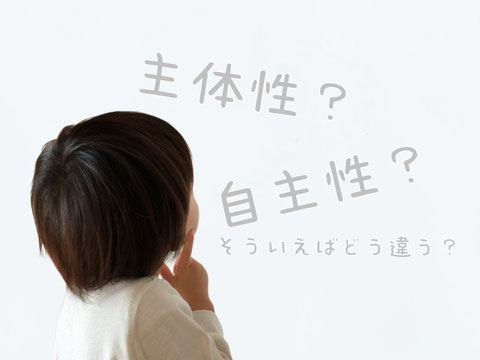
「自分で考えて行動する子」
を語るうえで「自主性」や「主体性」というのはよく使う言葉です。
「もっと自主的にやってみたら」
「クラスの子供たちの自主性に任せています」
「今の子は言われたことしか出来なくて主体性が足りないんですよ」など…
「自主性」と「主体性」
一見同じ意味合いにも思えますが、実はその意味は大きく違います。
「自主性」という言葉を使いながら「主体性」を求めていたり、無意識のうちに「自主性」と「主体性」を同時に求めていたりする人も多いです。
子育て支援の現場でも、この言葉の意味の違いを理解していない人と話していると、お互いの目的は同じはずなのに…意志疎通が出来ずお互いなんだかモヤモヤすることもあります。
「自主性」があって「主体性」が生まれると言われていますから、この意味の違いを知ることは大切です。
反対に、「自主性」と「主体性」の違いを知るだけで、子どもへの見守り方や接し方も変わります。
前置きが長くなりましたが、「自主性」と「主体性」の違いはここから。
自主性とは
やるべき行動を人に言われなくても率先してやること。
冒頭の学校の準備の例でいうと、
自主的な子は
「言われなくても翌日の日課を調べて教科書をランドセルに入れる」
「学校から帰ってくると連絡帳を親に渡す」
「授業中にトイレに行きたくなったら先生に言う」 など…
やるべきことを、先生や親に言われなくても自発的に行います。
子どもが上記のように自主性を発揮するためのポイントは
様々な場面において、その時自分がやるべきことが明確に分かっていることです。
主体性とは
何をやるかは決まっていない状況でも自分で判断して行動すること。
明日の学校の準備の例だと、
主体的な人は
「どうして前の日に準備するんだろう」と考えます。
そして
「忘れ物をしないためだ!」
「忘れ物をすると先生からの印象も悪くなる…」
「成績にも響くかもしれない!」
などと、やるべきことの目的を考えます。
もし、その目的を
「先生からの印象を良くして成績をあげたい!」
と決めたなら、前の日に準備をする以外に
「授業中に沢山手をあげよう!」
「ノートを綺麗に書こう!」
などと考えて実行していきます。
子どもが上記のように主体性を発揮するためのポイントは
「なぜこれをするんだろう」と行動の目的を考えられることです。
目的そのものを考えられるから、誰かに指示されなくても率先して行動を起こし、物事を進めることが出来ます。
まさに、親が子ども達につけてほしいと願う力です。
では、この主体性はどのように育てていけばよいのでしょう。
主体性を伸ばしたいなら「自主性」を育てるのが先

冒頭にもお伝えした通り、「自主性」があってはじめて「主体性」が育ちます。
様々な場面において、基本やルール、その場で決められたやるべきことを知らない子どもに、いきなり自分で考えて行動しろ!というのは、バスケットを知らない子どもに「試合で勝ってこい」とコートに放り出すようなもの。
子どもは何をしたらいいのか分からず不安と恐怖でいっぱいになるでしょう。
多くの親御さんがこれと同じように、子どもの自主性が育まれる前に主体性を求めて、出来ない子どもを責めています。
「子どもに自分で考える力をつけてほしい」
これ自体は素晴らしく絶対的に必要な考え方です。
ただ、ぜひ覚えていてほしいのです。
子どもにとって、自分のやるべきことを自信をもってやれるまでには不安というハードルがあり、そのハードルは親が思う以上に高いときがあることを。
子どもの自主性を育てる親の姿勢
やった方が良さそうだけど、自分のしようとしていることが間違っていないか不安…というお子さんは多いんです。
「不安」のある子の場合、行動が止まって見えたり「これでいい?」と何度も聞いてくることがあります。
そんな時…
「さっきも言ったでしょ!!」
「自分で考えなさい!」
などと突き放してしまうと余計自信を無くしてしまいます。
親の願う「自分のことは自分でする子」からドンドン遠ざかっていきますよ。
「これでいい?」
と子どもが確認してきたときは何度でも教えてあげてください。
優しく思い出させてあげるのもいいですね。
最後に、あるスポーツ少年団のコーチの言葉をご紹介します。
自分で考えて行動する子どもに育てるための接し方のヒントが見えると思います。
子どもの目的は常に「怒られないように」である。
だから、そこから主体性は生まれない。
主体性に繋がる自主性の育成には
まずは言葉で「やるべきこと」「なぜそれが必要なのか」を理論的に納得させ、「指導者の行動」で「感情的に」納得させる。
そうすることで、選手自ら体験し腑に落ちる。
「理論的に納得する」→「感情的に納得する」→「体験する」
これを繰り返し続けることで習慣化する。
習慣化するには根気と努力が必要ではあるが、そこで得た「自主性」は「主体性」へと変わり、子どもの可能性は無限に広がる。

急ぐ必要はありません。
時間がかかってもいい。
年齢だって関係ありません。
子どもにとって、「ひとつ自主的にやれた!」という事実が更なる自信を生み、確実に次の自主性に結びつきます。
だから、安心して見守ってあげてください。
子どもの自主性を育てるには根気がいる。
でも、その親の努力には、子どもの可能性という大きなギフトが待っています。
「何100回でも優しく教えてやる!」
と決心してみると、イライラも治まる気がしませんか。
▶こちらの記事も読まれています
-

-
話を聞いてもらうと子供の中にどんな変化が起こるのか-子供の話を聞かない親だと思われてない?
2022/8/9
あなたは子供の話を聞かない親だと思われていませんか?ここでは、話が聞けない人が勘違いしていいること、話を聞いてもらうと子どもの中にどんな変化を起こすのかをお伝えします。
-

-
マズローの欲求5段階説-子どものイライラは欲求不満のサイン!抑えられない子どもの欲求とは?
2024/11/8
抑えられない子どものイライラには理由がある 何を言っても言い訳ばかり… いつまでもグズグズする… 当たり前のことすらやら ...
-

-
中学生に親のモヤモヤをアイメッセージ(わたしメッセージ)で伝えてみた結果!【事例紹介】
2022/6/28
アイメッセージ(わたしメッセージ)を中学1年生の息子さんに伝えてみたという受講生さんの事例をご紹介しています。
-

-
「お決まりの12の型」を知っていますか?親業が教えてくれる親のNG対応
2022/6/28
子供の考える力を奪うこともある「お決まりの12の型」を事例でご紹介しています。

