子育てが上手くいかないとき知りたい発達心理学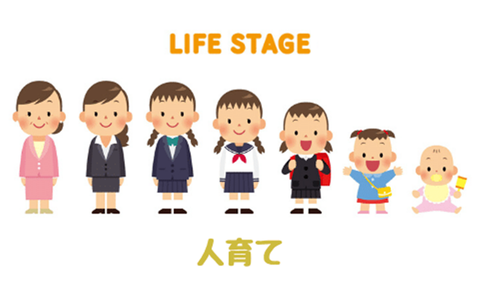
「心と行動の学問」と呼ばれる心理学。
その中でも、人の心と体が一生を通じ成長、発達していく変化の過程を研究したのが発達心理学です。
発達心理学を知ることで、「どうしてこんなことも出来ないの!」とイライラしていた子どもの行動が、「この年齢だと出来なくて当たり前」「もっと年齢にあった教え方に変えてみよう」と育てる側に余裕が出来ることも多いです。
発達心理学といえば、エリク・H・エリクソンの「心理社会的発達理論の8段階」、フロイトの「リビドー発達段階理論」、そしてジャン・ピアジェの「認知発達の4つの段階」が3大発達段階説とも呼ばれ大変有名です。
ピアジェの発達段階とは?
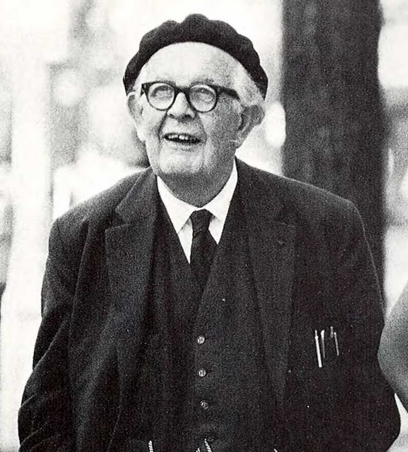
ウィキペディアより (1968 年のミシガン大学年鑑)
ジャン・ピアジェは、スイスの心理学者。20世紀において最も影響力の大きかった心理学者の一人です。
子どもの発達段階を、認知発達理論で分類した「ピアジェの認知発達の4段階」は、子どもの言語、世界観、因果関係、数や量の概念などがどのように発達するかを理解するうえで大変役に立ちます。
ここでは、発達心理学の父とも呼ばれるジャン・ピアジェの「認知発達の4つの段階」をわかりやすく解説します。
ピアジェの認知発達の4つの段階

1.感覚運動期(0〜2歳頃)
赤ん坊はこの時期に身近な環境に関わり、吸う、つかむ、たたくなどの身体的な活動を身につけます。
この段階の特徴は「循環反応」と「対象の永続性」
▶循環反応とは
ふと何かを触ってみたら感触が面白かったので、何度も触ってみる、といったこと。
▶対象の永続性とは
物を見ることができなくても、物が存在し続けていることを理解する能力のこと。
-生後7~9ヶ月頃になると、物の永続性を理解し始める。 例えば、ブランケットの下に子どものお気に入りのおもちゃを隠した場合、子どもは物理的におもちゃを見ることができなくとも、ブランケットの下を探そうとするようになります。
そして、この能力を獲得するからこそ、赤ちゃんは「いないいないばぁ」を楽しむことができるよのです。
人の真似がドンドン上手になる
この感覚運動期は赤ちゃんの「模倣行動」が発達する時期です。
▶ピアジェの理論における模倣行動の発展水準は以下の3つに分類されます。
~生後8カ月頃
(手の運動と発声の模倣期)
自分が見たり聞いたりできる、自分と相手の動作・発声のみを模倣できる。
生後8カ月~12カ月頃
(顔の模倣期)
前段階と異なり、見ることのできない自分の表情を、相手の表情に近づけることができる。
生後18カ月~
(延滞模倣期)
相手の動作を記憶し、あとから模倣できる。
2.前操作期(子どもが話し始める頃~7歳頃)

この段階の子どもたちは、心の中で行う計算のような特定の認知的操作を行うことができないため、日常生活においてさまざまな物体、出来事、状況に遭遇するとき、言葉や画像を含む精神的なシンボルを使いはじめる。
加えて、子どもたちは彼ら自身ではない人々(例えば、先生やスーパーヒーロー)の真似をするごっこ遊びに没頭し始める。
また、さまざまなおもちゃを使って、ごっこ遊びをより現実に近づけようとしていきます。
この頃の子どもの世界観
前操作期の子どもが世界をどう認識するか重要なキーワードが「実念論」「アニミズム」「人工論」の3つです。
実念論
自分のものの見方が絶対的だと思い込む。
アニミズム
非生物にも人間のような思考や感情があると思い込む。
人工論
自然物も人間が作ったと思い込む。
さらに、前操作期は「象徴的思考期」と「直観的思考期」に分けられるます。
「象徴的思考期」(2~4歳)
象徴的思考期の子どもは、もののイメージを作り上げて頭のなかに保存し、あとで取り出して使うことができるようになる。
つまり、目の前にないものを思い出し、絵に描いたりすることが可能になる。
2~3歳の子供は「模倣期」にあり、日常生活における大人の様々な動作を真似をしたがる時期。
3~4歳くらいの子どもたちはしばしば、自己中心性を示します。
■自己中心性とは
相手の立場で想像することができず、たとえば自分の知っていることは当然相手も知っているだろう、他の人が自分と同じ出来事を経験し、同じ感情を持っているだろうと思い込んでしまうこと。
「直観的思考期」(4~7歳)
直観的思考期の子どもは、経験したことのない状況を説明するとき、絵本のような空想ではなく理性を用いるようになります。 ■中心化とは 対象のうち最も目立つ側面だけに注意を集中して、それ以外の部分を無視すること。
例えば、「家が地面から生えてきた」ではなく、「人間が材料を組み合わせて家を建てた」と言うように。
しかし、まだ論理的思考にはいたらず、中心化という思い込みの特性を有しています。
例えば、口径の広いビーカーに水が入っているとして、それを子どもの目の前で細長いビーカーに移し替えます。
すると、子どもは高くなった水面ばかりに意識が向き、水の量が増えたと思い込んでしまうこと。
この思い込みは、中心化という特性によるものです。
前操作期の特徴
■記憶表象が未発達で、原則として実物しか推論の操作対象にすることができない。
■時間や空間的な制約に縛られており、言語を用いた思考はまだ不得意。
■他者の存在は自覚しているが、自分との区別があまり明確ではない(強い自己中心性) 。
■目の前にある実在物に依拠した推論にしたがう。見た目に大きく影響を受ける。
■基準にしたがって分類したり並べ替えたりすることが不得意である。
■対象の永続性といった再認記憶が確立される。再生記憶については未発達。
3.具体的操作期年齢(7歳頃~11歳頃)

この段階で重要なのは、子どもが「保存の概念」を理解できるようになることです。
保存の概念とは
ものの見た目が変わっても、ものの量や数が変わるわけではないという概念。
例えば、短く幅の広いカップに入った液体を、背の高い、痩せたガラス容器に移し替えるなどしても液体の量は変わらないこと。
論理的な思考をしはじめる
「保存の概念」を獲得していくこの段階から、子どもは論理的思考をしはじめます。
それに伴い前の段階の自我主義が消え、誰もが必ずしも同じ思考、感情、および意見を共有するわけではないことを理解し始めます。
そして、他の人がどのように考え、感じているのかを考え始めるようになります。
しかし、この時点で抽象的なことや仮定(もしも○○だったらなど)についてはまだうまく考えられず、大人が当たり前に使う抽象的で仮説的な概念に苦しむ傾向があります。 抽象的とは 共通した要素を抜き出して一般化していること、または具体性に欠けていて実態が明確ではないこと。 具体的操作期の特徴
例えば、「犬」を説明する際に「四本足の動物」といえば抽象的に述べたことになり、「我が家のペットで白くてふわふわした8歳のメイちゃん」といえば具体的に述べたことになります。
実用日本語表現辞典より
■内面化された心的操作を利用できるようになる。
■他人の心理状態を推測できるようになる。
■数、量、長さ、重さ、体積、時間、空間などの科学的な基礎概念が獲得される。
■仮想的な事実についての推論はあまり得意ではない。
4.形式的操作期(11歳〜 )
この段階になると、抽象的なものや仮説上の出来事についても合理的、系統的に考えられるようになる。
▶子どもが形式的操作期に入ったかどうかを確かめるには
「ケリーはアリーより背が高く、アリーはジョーより背が高いとしたら、身長がいちばん高いのは誰かな?」
のような質問をしてみると分かります。
形式的操作期にいる子ども…頭のなかだけで考えて答えを出すことができる。
まだ具体的操作期にいる子ども…絵を描かないと分からない。
形式的操作期の特徴
■自分で実際に体験したものでなくても、説明・映像などから具体的なイメージを描くことができる。
■具体的な事象・時間の流れに捉われずに「物事を広い視点で考える」ことができる。
■これまで得た知識・経験を応用して仮説を立て、結果を予測して行動・発言することも可能です。
子どもの道徳観について
ピアジェは、2つの発達段階があると主張しました。
他律的道徳観(5~9歳)
この段階の子どもは、道徳とは他人の作ったルールや法律に従うことで、それらは絶対に変えられないものだと思っています。
そして、ルールを破ると厳しい罰を受けなければならないと信じています。
他律的道徳観の特徴のひとつは、行動の意図よりも結果を重視して善悪を判断するところにあります.
他律道徳観の場合
例えば、「親が掃除するのを手伝おうと思い、洗剤を大量にこぼしてしまったAちゃんと、洗剤で遊んでいたら少しだけこぼしてしまったBちゃんがいるとした場合」
他律的道徳観の段階にいる子どもに、「どちらがより悪いか」を尋ねると、「Aちゃんが悪い」と答えるのです。
自律的道徳観(9~10歳)
この段階の子どもが持つ道徳観は、自分自身のなかにあるルールに左右されるようになる。
また、自律的道徳観の段階にいる子どもは、絶対的な善悪は存在しないことを理解し、他人の視点からも考えられるようになっていきます。
自律的道徳観の場合
例えば、先ほどの「手伝おうとして洗剤を大量にこぼしたAちゃん」と「遊んでいて少しだけこぼしたBちゃん」の場合。
自律的道徳観の段階にいる子どもに、「どちらがより悪いか」を尋ねると、「Bちゃんが悪い」「Aちゃんも良くないけどBちゃんも良くない」などと答えるようになります。
他律的道徳観から自律的道徳観に変わっていくことで、他人の意図や状況も考慮に入れ、ルールや道義的責任、罰などの判断力が大人に近づいていくのです。
参照:こころの探検 /ウィキペディア/ こどもまなびラボ /Piagetによる思考の発達段階説
まとめ
ピアジェの発達理論で子どもの認知(ものの見方、とらえ方)の変化を知ると、「あ~だから本気でヒーローやヒロインになりきれるんだ」と腑に落ちたりします。
いつまでもアニメキャラクターの話を聞かされる親はたまりませんが(笑)
いつかはこの無垢な心は失われていくんですよね。
親の後悔のひとつに、「子どもの話をもっと聞いてあげればよかった」をあげるひとは少なくありません。
いつまでも子どもの話しにつき合うのは大変ですが、たまには「今日は子どもの空想の世界を楽しむぞ」と決めて会話をしてみるのもいいのではないでしょうか。
こちらの記事も読まれています
・マズローの欲求5段階説-抑えられない子どもの欲求とは?
・脳科学まとめ<9歳~12歳編>小学校高学年の発達
・自分で考えて行動する子供になってほしい「自主性」と「主体性」の違い
・話を聞いてもらうと子供の中にどんな変化が起こるのか
・子供の忘れ物を届ける?届けない?
・「お決まりの12の型」親業が教えてくれる親のNG対応








